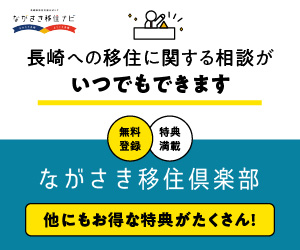桜前線も北上していますが、皆さまの地域では桜の便りは届きましたか。壱岐では寒く強い北風も和らぎ、花が咲き、鳥が歌い、ぽかぽかとした陽ざしが降り注いでいます。
さて、3月1日から始まりました、壱岐の真珠養殖場『上村真珠』さんの浜揚げを見学しました。社長にお時間をいただき、インタビューを行いましたのでご紹介いたします。
|輝くその日まで
───生産量はどのくらいですか。
「一個の真珠ができるまで、貝が生まれてから2年目で作業(核入れ等)を始めて、4年目で収穫になります。
真珠の尺貫法で言うと200貫で、わかりやすくキロ数で言うと、大体700㎏くらいあります。
一つの貝に貝柱が一つずつ入っているけど、貝柱3,500kg分くらい獲れます。 」
▼浜揚げの様子の写真。20日ぐらいかけて、洗浄や仕分け、選別をしています。



▼アコヤ貝の貝柱を分けている様子。水揚げの時にしか取れない、大変貴重なものです。
コリコリとした歯ごたえが特徴で、お刺身はもちろん、炊き込みご飯やバター焼き、かき揚げなどにすると美味しいです。


───いちばん苦労する工程はなんですか。
「全部苦労はするんだけど、一番重要なのは貝の子供を作るときかな。
それが一番神経を使いますね。
最初のオスとメスの掛け合わせで遺伝子の違いや、貝によって品質の良い悪いがありますから、その掛け合わせを失敗すると、いい貝もいい真珠もできない。
自分で交配して、稚貝を育てて、真珠を収穫するのが楽しい。
『自分でこうだと思って作った貝がこうなるんだ』と考えて毎日過ごすと飽きない。」
▼採れたての真珠。真珠本来の色が見えます。

▼自然光の当たる窓辺でチェックしていました。よく見ると、少しずつ色の違いや形の違いがありました。



|貝と海と個性
───貝や海が相手だと大変ではないですか。
「貝っていうのは小さな生き物だけど、いろんな表情を持っていて、一個一個個性があります。元気がなくなると人間と同じで、肌が悪くなったり、カサカサしたりする。貝柱も、いかにも美味しくなさそうな肉になる。
元気があってつやつやしてて、見た目もぷりっとしていい表情の貝は、貝柱が大きく弾力性をもってて、その中で育っている真珠は輝きがあって、巻きがあって、透明感もある。
単にアコヤ貝っていうけど、一個一個個性がある。海も同じで、いろんな表情をもっている。
沖の方から死滅させるプランクトンが来ているのを入口の近くで見つけると、今吊っている養殖の棚にロープを足して下げたりして、その層を回避すると、早ければ早いほど(アコヤ貝が)助かる。
そうやって、海の表情を先にとってあげると、災害とかも防げたりできる。 」
▼半城湾と上村真珠養殖場。きれいな海と豊かな緑に囲まれています。

───なぜ真珠の色に違いがでるのですか。
「白も黒も自然の色だけど、真珠の元となる核入れをしたときの状態によるものがほとんど。
元気のない貝が手術すると回復まで時間がかかるから、その間に真珠層ができる前に雑菌が入って黒くなる説もある。
それも1個の真珠。
白くて綺麗なやつもあれば、黒いやつもいる。
でも、黒くていいやつもある。
昔から真珠は『巻き』『照り』『色目』の3つの要素があって、人の目がみて綺麗って思う色、ピンク・グリーン・ブルーがある。
でも、統一で綺麗と思うのは、真珠をみたときに自分の顔が映る真珠っていうのが、一番綺麗。
色は関係なしで、鏡の面ができてる。
ほんとの真珠の色が輝くには『鏡の面』を作る作業が大事。 」
▼12年前に採れた最高品質の真珠。手で持つと目や鼻がわかるぐらい反射しました。これをネックレスとして売ると、レクサスが買えるそうです。経年劣化が遅く、きれいな状態を保てるのは品質が良い証拠。

取材後記
真珠の魅力などを語る社長は笑顔がとても素敵でした。
社長が心からアコヤ貝と真珠が好きで、楽しそうに語るからでしょうか、お話を聞くうちに「ここの真珠が似合うような女性になりたい」と思えてきました。
この綺麗な真珠には、アコヤ貝と壱岐のキレイな海と上村真珠の想い、どれひとつ欠けてはいけないのだろう、と感じました。
ご協力いただいた生産者さん『(株)上村真珠』
真珠の主な出荷先は、世の女性が憧れるジュエリーブランド「MIKIMOTO」。
「平成26年 全国真珠養殖漁業協同組合連合会会長賞を受賞」「平成30年 全国真珠品評会において、農林水産大臣賞を受賞」他多くの賞を受賞。
今は壱岐・対馬・福岡などを合わせて、110人ほどのスタッフが養殖・加工・販売に携わり、その内の約7割80人くらいのスタッフが、一番大きな壱岐の養殖場で働いている。
(株)上村真珠 本社 創業 昭和25年
福岡市中央区平和5丁目10番10号
壱岐本場 養殖場
長崎県壱岐市郷ノ浦町半城本村触1347
◇壱岐市ふるさと納税 返礼品◇
───上村真珠の返礼品───
───壱岐産アコヤ貝───
Photo by 髙田望