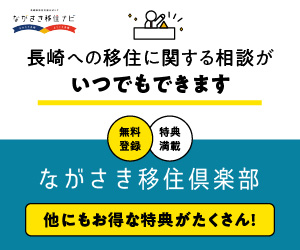「まちづくり協議会」とは、地域の課題解決のため、また、安心していつまでも住み続けられるまちづくりを行うため、地域住民の皆さまをはじめ、自治公民館や各種団体で構成する、地域住民による自発的な組織です。
範囲は4町からさらに細分化されており、小学校区を1単位で現在は15校区で設立されています。それぞれの地域に居住している人や、働く人、学ぶ人などが自らのまちの活性化のために協議を重ね、活動しています。
このいきしまだよりの記事内で、それぞれの「まちづくり協議会」の活動の一部を、今回よりシリーズ形式でご紹介をさせていただきます。これから移住を検討されている方や、すでに移住された方も、地域の皆さまが一体どんな課題と向き合い、まちづくりを行っているのか、ぜひ読んでみてください。
【郷ノ浦町】SOH(Sustain Our Hatsuyama)~我が初山を持続させる~
(1)初山地区ってどんなところ?
初山地区は壱岐島南部に位置し、東西約4.7km、南北約4.1km にまたがり、面積は約9.1km2 です。北部は壱岐島で1番標高が高い岳ノ辻(213m)の裾野となっており、中央に壱岐島で2番目に高い(175m)の久美ノ尾がそびえ立ちます。
北部以外は玄界灘に囲まれており、その海に向かってなだらかに傾斜している地形です。このため、風光明媚な景色が広がっており、夕日や漁り火が絶景です。
主要路線として、一般県道渡良浦初瀬線(175号線)、一般県道初瀬印通寺線(176号線)、1級市道片原若松線が、周囲を取り囲んでおり、1級市道初山中央線が中央を横断しています。
(2)初山地区まちづくり協議会について
初山地区まちづくり協議会では、下記の基本方針をもとに課題に対して地区全体で考え、手を取り合い、解決に向かって実行に移します。
人口減少とともに行事などが衰退化し、活気が失われつつあります。しかし誰もが、ふるさと初山を後世に残すことを望んでおり、それは今初山に住む私たちの責務だと思います。
そのため、『SOH(Sustain Our Hatsuyama)(我が初山を持続させる)』をテーマとし、3つの持続を基本方針とします。
すばらしい景観を持続する初山
住みよさを持続する初山
人とのつながりを持続する初山

―初山地区まちづくり協議会から見える景色 海の向こうには三島が見える
(3)初山地区まちづくり協議会、支援員の日樫(ひがし)さんに話を聞きました。
——地域の交通手段として、独自の取り組みがあると伺いました。
「初山地区まちづくり協議会では、壱岐市内で初の地域コミュニティバス『オレンジバス』の運営を行っています。これは、交通の便が悪い初山地区において、通院や買い物、通学などの“地域の足”として機能する交通手段です。事前予約制で、車両は10人乗りの小さなバスです。地域の方4人が交代で運転を担当していて、地域みんなで支え合う形が実現できています。車体の側面には、初山の名所『海豚鼻』にちなんで、イルカのイラストが描かれていて、地域の人たちにも親しまれています。オレンジバスで登下校している小学生もいます。」

―初山放課後子ども見守り教室(現在は、卓球がブーム!!)
——観光スポットはありますか?
「鏡嶽神社、海豚鼻、初瀬の岩脈、六人地蔵、夕日スポットなど、地元にとっては“あたりまえ”すぎて見過ごされている場所がいくつかあります。初山に住んでいる方の話を聞くと、もっと観光地をアピールしたいとか、きれいな夕日を見てもらうために観光地にしたいなどのアイデアがたくさん出てきます。地域の方たちと一緒に観光地の開発をすすめ、将来的には、観光マップやガイドツアーなどに発展できたらと考えています。」
——“つながり”も大切にされているそうですね。
「初山では、子どもも高齢者も“地域全体で育てる・支える”文化が自然と根づいています。たとえば、凧揚げや昔遊びをテーマにした世代間交流イベントは、子どもたちも高齢者の皆さんも毎年楽しみにしている行事のひとつです。旧初山中学校のグラウンドにはペタンクコートを整備し、今では小学生と老人会の皆さんが一緒にプレーしています。こうした活動を通じて、世代を越えた交流が生まれています。また、漁師さんや農家さんが獲れた魚や採れた野菜を近所に配るなど、日常的に助け合う風習も残っています。“みんなが名前と顔を知っている関係”は、子どもたちにとっても大きな安心感につながっているように思います。」

―明るく気さくにお話ししてくれた、支援員の日樫さん
——地域の環境整備にも力を入れていると伺いました。
「“イベントは1回で終わる、継続して取り組めることをしよう”という後藤会長の方針のもと、日常的な地域の整備活動を大切にしています。もちろん、公民館単位でも除草作業は行われていますが、まち協としては、特に観光地としての魅力を高めるために、『海豚鼻』や『久美ノ尾』など、初山にある自然スポットの除草作業に力を入れています。地域の景観維持や観光客への印象向上にもつながっていると思います。」
——今後の展望を教えてください。
「持続可能な地域づくりのためには、子どもたちの視点を取り入れ、未来を一緒につくっていくことが欠かせません。大人が主導するのではなく、子どもたちの発想や気づきを尊重しながら活動していきたいです。将来、地域を担うのは今の子どもたちですから。」

―オリジナルの初山Tシャツ(舞台は鏡嶽神社)
未来を担う子どもたちの声に耳を傾け、共に歩む初山地区まちづくり協議会の取り組み。その姿勢は、世代を超えて“つながり”を紡ぎ続ける地域の大きな力となっています。オレンジバスをはじめとする地域密着型の取り組みは、日々の暮らしを支えながら、未来を見据えたまちづくりへとつながっています。これからの初山がどんな未来を描いていくのか、ぜひ注目してみてください。